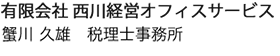競争力と商品・撤退障壁 事務所便り2016年7月19日(火)No399

競争力と商品
ある会社は競争力を持ち、別の会社はそうではない。その理由について説明が不足している。
繁栄しているか、支配的地位にあるか、それは何故か、高い生産性と効率の増大を達成する会社の能力差です。
その理想を追求する力、実現する力。逆に言えば損を確定できる実行力です。
また、顧客を創造する競争力が、儲ける力です。
親方日の丸思想は、地方において強く存在しています。そもそも政府の官僚は内外の演技者であって競争のスター役を演じることはない。
政府が介入する産業の大部分は、成功しない。国際レベルでそうであって、国内レベルでも成功していない。直接の当事者ではない県市町村を含め官僚の無責任が、その理由です。
会社の人的資源の生産性が競争力を高め、高水準で生産性を達成し、長期間に渡り生産性を増加する競争力に掛かっています。
それらの実現は、各人は自覚し、自らでグレードアップする必要があります。
会社で各人の生産性とスピードが、競争力の根源です。
この競争行動を取らなければ確実に敗者になる。
模倣できるそれ以上の速さで、先に新たな優位性を築かなければなりません。
自らの意志で重大な改善や戦略変更を殆どされていないのです。実際は環境に追い詰められ、その時点で追従するだけです。
ニーズを探らず、反映しないとしたらそれは明らかに競争で劣勢に立っている。
従前と同じ繰り返しをすれば、少なくとも少しは存続する保証はあるでしょう。
実際前期と比較して大きく変化はないでしょう。
さほどの変化を感じていなければ、実際は停滞どころか衰退しているのです。数字を見て、これから頑張れば良いと思ってしまうことが多いのです。
自分の立場や社会情勢や環境の捉え方で、社会の変化を、発展と捉えるか衰退と考えるかで現状認識が全く異なってきます。
結果が前年比、マイナス又は零点数パーセント増なのでしょう。
競争からの防衛能力である攻撃能力を忘れ語る人がいます。視野が狭くないでしょうか。
改革とイノベーションの必要性でなく、積極的目標のない単なる存続は、提供する商品は従前である過去が当然基本ベースです。
その過去の延長線上で幻想に酔い、未来の消滅危機の存在が、見えないのは当然です。
人は不都合を見ない、言わない、考えないものです。
それぞれの業界は全て新規参入・競争業者・買い手・売り手・代替え品の五つの構造になっています。
これらの中で収益性が低いほど買い手の交渉力は増え、売り手の重要性が減少します。
全て業界の売り手は商品の買い手を選択しなければならない。売り手の商品は更に買い手の収益性を高めるものでなければならない。
小規模事業者に限らず借入金は、利益の先食い。完済までの間、損失金です。
薬物に手を出せば簡単に依存症になれます。
貸す金の責任を免除される社会は、誰もが金融資本の奴隷になり得ます。
撤退障壁
先送りの時間稼ぎで問題が解決する? 政権は構造改革の旗を降ろしていません。
どうしても結論は経営者の感情障壁の問題になります。
撤退経験のない経営者ほど判断に苦しみます。
判断が出来ず誇りが傷つき、永年の思い入れを失い躊躇するのは人間的ですが、経営者の社会的責任から誰も逃れ免除されません。始める時に撤退基準を設定し、その基準をどれだけ守れるのでしょう。
実際撤退コストは固定コストに限らず、先に書く見えないコストがあります。
永年どんな商品で、何を売ってきたか。これからも同じか。地上は栄枯盛衰、諸行無常であります。
これまでの時は取り戻せません。勝敗は決している?その決断が未来を失うものか。
頑張り、どれだけマイナスを減らすのか。