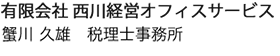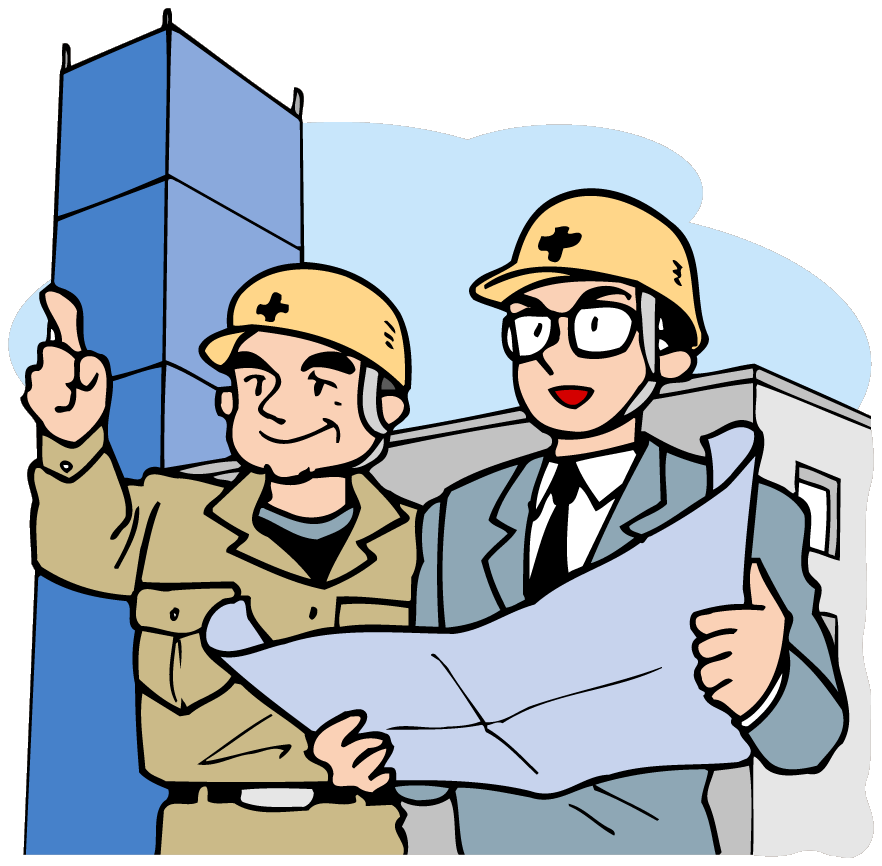災害列島・利他の目標 事務所便り2018年9月18日(火)No446
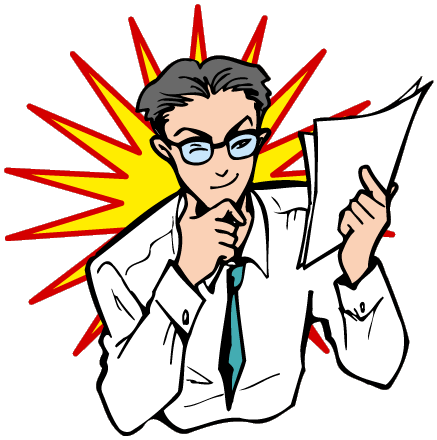
災害列島
台風一過の近畿・能登、北海道大地震で危害を受けた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
災害の状況が明らかになるにつれて基本的な弱点・見えない問題点があぶり出されて来ています。
想定を簡単に超える現象です。
私は単独登山が趣味です。結果は全て自己責任ですから、入るときは複数のライフラインの最低限を装備します。一瞬の油断や想定外は直、ケガと遭難です。
我国を鍛えるため試練を与え、コスト優先のエネルギー・インフラの脆弱性を災害の「絶対的力」で、あぶり出し試すのでしょう。
現在家計に占める食料品の金額割合は、2005年を底に食料品と光熱費が、10%を超える上昇です。この間、消費者物価は3.3%の上昇でしたが二桁の上昇、これは吐出しています。
打撃を最も受けるのは低所得者や高齢者世帯で、家計を直撃しています。
生鮮魚介類はこの間23.0%平均価格の上昇でしたが、購入数量は35.5%のマイナスになっています。生鮮肉は2.8%の価格上昇に対して購入数量は17.6%も伸びています。
この10年間で食料品の支出額が5%増加していますから、食料品価格の11.8%上昇を差し引けば、差額6.8%も家計の購入数量が減少していることになります。
価格が上がったビールは38.3%減少し、価格が下がったワインは53.8%消費量を増やしています。
即ち低所得者や高齢世帯のエンゲル係数が上昇しているのです。
食料品やエネルギーの価格は、国際商品市場の影響を受けますので、景気や金融政策から離れて決まってきます。
エンゲル係数の上昇は、コストプシュ・インフレの影響で現れます。
他に回る購買力を奪っていきますから、当然にデフレ傾向を強めます。
日銀の政策、2%目標がいつまでも達成できないのは、コストプシュ・インフレの作用で、実質の購買力を減殺しているのです。
円安になって輸入物価が上昇して、家計の実質購買力は下がっていくことになっているのです。
現在無職世帯が40%台に迫っており、年金制度は物価に対して1年遅れのスライド制度と、年金支給額の固定的なことに、何ら問題はないのでしょうか。
トランプは、小学校5年生並みの理解力しかないと側近に書かれていますが、アベ氏は追随する危険を理解されているのか心配です。
戦後マッカーサから、日本は小学生並みと揶揄されましたが、お互い様です。
圧倒的権限を持つトランプとアベも、同じ災害でしょうか。
利他の目標
旅人がとある街に向かう道を歩いていると、一人の男が辛そうにレンガを積んでいました。
旅人はその男に向かって「ここで何をしているんですか」と問うてみました。
するとその男は「見ればわかるだろう。レンガを積んでいるのさ。」と答えました。
もう少し歩き続けると一生懸命レンガを積んでいる別の男に出会いました。
旅人はその男に向かって「ここで何をしているんですか?」と問いました。
その男は「壁を作っているのさ。早く仕上げたくてね。」と真顔で答えました。
またしばらく歩くと生き生きと楽しそうにレンガを積んでいる別の男に出会いました。
旅人はその男に向かって「ここで何をしているんですか?」と問いました。
その男は「みんなが集まり、幸せになれる家を作っているんだ。素晴らしいだろう!」と嬉しそうな顔で答えました。